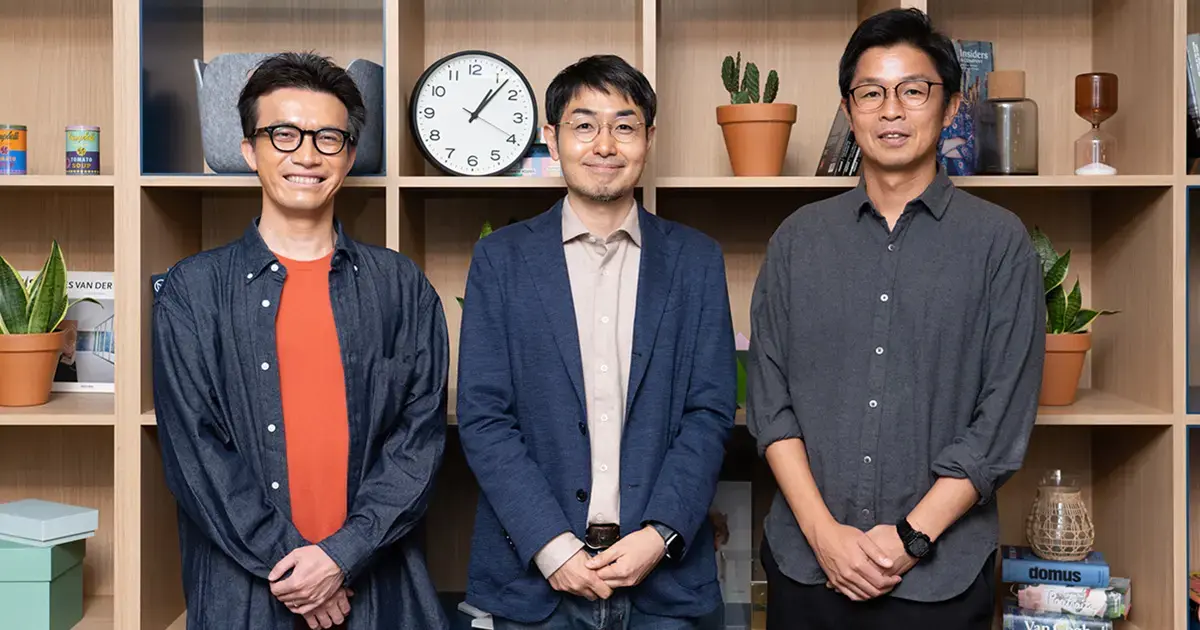教育機関 京都芸術大学附属高等学校
CTRはメールの約1.5倍に!ステップ配信とAIチャットで広がる進路サポート

プロジェクトの概要
- 初回接触後の継続フォローが弱い
- HPにFAQはあるが問い合わせハードルが高く、本音が拾いにくい
- 少人数体制で配信・管理の負荷が大きい
- セグメント配信やステップ配信での効果的な運用
- AIチャットボットの活用
- LINEとHubSpotを連携し、一元管理を実現
- LINE配信での高パフォーマンス
- AIチャットボットで心理的なハードルを低減
-
少人数の運用でも継続可能な体制を構築
取り組みの内容
提供事業
京都芸術大学附属高等学校は、京都芸術大学を母体に2019年に開校した高等学校です。通学型の「新普通科」に加え、2025年春にはオンライン型の「じぶんみらい科」を開設し、コミュニケーション力・協働力・発想力を培う環境を提供しています。
今回導入いただいた「じぶんみらい科」では、「教室を出たら、冒険だった」をテーマに、オンラインで全国から生徒が参加。デザイン思考や教科横断の探究学習、芸術教育を通じて、感性を磨きながら自ら考え、行動し、新しい価値を生み出す力を育成しています。変化の激しい社会に求められる創造性や人間力を育むことを教育の柱とし、従来の枠にとらわれない学びを展開しています。
◆学校公式サイト
https://shs.kyoto-art.ac.jp/
導入の背景
今回インタビューに応じてくださったのは、京都芸術大学附属高等学校 入学広報担当の作山さんです。企画からSNS運用、分析まで幅広く担い、新設された「じぶんみらい科」の立ち上げに携わってきました。
その中で直面したのは「生徒や保護者にどう情報を届けるか」という課題。新しい学科を日本全国に広く知ってもらう必要がある一方で、デジタルマーケティングの基盤はまだ整っていませんでした。特に、生徒や保護者が日常的に使うLINEをどう活用するか、そしてそれを顧客データとつなげる仕組みをどう構築するかが大きなテーマとなっていました。
そこで導入を決めたのがLITTLE HELP CONNECT。LINEとHubSpotを連携させた一体的な運用によって、開封率約80%・CTR約15%という高い成果を実現しました。さらにAIチャットを活用することで、生徒や保護者の“人には言いづらい本音”も拾えるようになりました。
ステップ配信・セグメント配信で「届くべき人」に響く戦略へ
作山さん:
日本全国で学べるオンラインタイプの学科として広報するにあたって、「誰に・どんな情報を届けるべきか」を手探りで模索していました。限られたリソースのなかで効率よく情報を届けるためには、一斉配信だけでは不十分で、対象を適切に絞り込む工夫が必要でした。
LITTLE HELP CONNECTの導入により、ユーザー属性や行動に応じたセグメント配信が可能に。まずは大まかな条件から始めても十分な成果が得られました。
さらにステップ配信を取り入れたことで、メッセージが一方通行にならず、ユーザーにとって必要な情報がタイムリーに届くように。結果として、LINE配信は開封率約80%でメールの約2倍、CTRは約15%でメールの約1.5倍の成果を実現しました。
今後は地域や行動履歴など、より細かな切り口での配信も検討しています。
AIチャットで“気軽な本音”を引き出す
京都芸術大学附属高等学校がAIチャットボットを導入したきっかけは、「もっと気軽に相談できる窓口をつくり、ライト層も取りこぼさずにすくいたい」という思いからでした。従来の問い合わせフォームや説明会だけでは、関心はあるけれど一歩を踏み出せない層に十分アプローチできない課題があったのです。
作山さん:
導入支援の際には、“人相手だと緊張しやすい内容も、AIなら気軽に聞ける”という活用視点でアドバイスを受けました。その結果、実際の運用でも心理的なハードルが下がり、「勉強についていけるか不安」「一人だと続けられるか心配」といった率直な声が集まるようになりました。
「伝える」よりも「聞く」かな。心の声を「聞く」という意識で、問い合わせフォームや説明会だけでは拾えなかった“本音”を引き出す新しい窓口として機能しています。
一元管理で“省力化”と安定運用を実現
従来は問い合わせや資料請求があっても、後続フォローが追いつかず、初期の関心を活かしきれない課題がありました。さらに少人数体制のため、配信や予約管理の負荷が大きく、継続的に運用するのが難しい状況でした。
導入後は、友だち追加や資料請求といったデータが自動でCRMに統合しLINE配信され、担当者が手作業で追う必要がなくなりました。
この仕組みによって、工数を抑えながらも少人数で継続的に発信できる基盤が整いました。

今後の取り組み
実際にお話を伺うなかで印象的だったのは、作山さんが生徒一人ひとりにどう寄り添うかを真剣に考え、施策を楽しそうに語ってくださったことです。
そんな熱意の中から、今後取り組んでいきたいことや、LITTLE HELP CONNECTへの期待についてもお話を伺いました。
作山さん:
今後は、説明会や体験授業への参加を促すためのナーチャリング施策を強化していきたいです。現状、リッチメッセージは画像1枚やカルーセルの2パターンしか使っていませんが、もっと多様な形式を試して、生徒や保護者の関心を引きつけられるようにしたいと思っています。
LITTLE HELP CONNECTへの期待としては、レポート機能の改善ですね。今は一部のデータを確認するのにエクスポートが必要なので、ダッシュボード上で直感的に見られるようになるとありがたいです。
さらに、配信結果の振り返りも定期的に行えると心強いです。こちらも日々忙しくて後回しになりがちなので、カスタマーサクセスの方からミーティングを設けてもらい、開封率やCTRを一緒に確認しながら改善点を議論できる場があれば嬉しいです。
その他の記事
その他の導入事例についてもご覧ください